経済が変わる。
社会が変わる。
価値観が変わる。
これまで「当たり前」だと思われていたグローバルスタンダード――
その多くが、実は一部の文化圏によって作られた“偏った常識”に過ぎないのではないか。
そんな疑問を私たちに突きつけてくるのが、日下公人氏の著書『日本発の世界常識革命を』(ワック刊)です。
日下氏の発想は、実に本質的で、常識を疑う鋭さを持っています。
彼は言います。
「数百年続いた白人優位の文化観が終わりつつある」と。
私たちはこの潮流を単なる評論として聞き流すべきではありません。
経営コンサルタントとして世界の動向を注視する中で、これは今後の日本企業が持つ“独自性”を再定義する好機だと確信しています。
日下氏は、こう問いかけます。
- 世界全体の調和を本気で考えてきた国はどこか?
- 宗教的対立を生まない、平和と清浄を説く思想はどこにあるのか?
- 神話において女性を尊び、自然と共生してきた文化は?
- 満員電車で「チカン!」と女性が叫べば、周囲が即座に加勢する社会は、世界の中でどれほど存在するのか?
それらの問いに、日本は確かに静かに、しかし確実に答えを持っています。
私たちが日常で何気なく実践している「譲り合い」や「空気を読む力」、「調和を重んじる価値観」は、世界のビジネスパーソンから見ると“異質”かつ“高次元”な知恵です。
西洋的な競争原理や成果主義だけでは行き詰まる今、「共生」「礼」「間」「和」の思想こそが、未来のリーダーシップに必要とされ始めています。
トランプ大統領が「アメリカ・ファースト」を掲げて既存秩序に風穴を開けたように、いずれ日本が「ニッポン・ファースト」を掲げるときが来るかもしれません。
ただしそれは、他を排除するものではなく、「他をも活かす、静かなる強さ」による主導です。
日下氏は、こうも指摘します。
「日本の思想には“負けるが勝ち”という価値観がある。表面上の損失が、長期的には勝ちにつながるという考え方だ」
この発想は、短期利益を追う多くの経済合理性と真逆です。
しかし、だからこそ世界が今、惹きつけられているのです。
経営の世界でも、日本型経営の再評価が進んでいます。
単なる終身雇用や年功序列ではなく、「信頼の積み上げによって組織を強くする」日本独特のマネジメント哲学にこそ、持続可能な組織運営のヒントがある。
私たち日本人自身がまだその価値を十分に認識する時が来たのかもしれません。
グローバルスタンダードに“合わせる”のではなく、これからは“創る”側に回りましょう。
日本の常識が世界をリードする。
その胎動はすでに始まっています。
この潮流を経営にどう活かすか――
今こそ、日本的知恵のリデザインが必要なとき。
私たち一人ひとりが、自国の価値観に誇りを持ち、それを軸に世界と向き合う時代が到来しています。
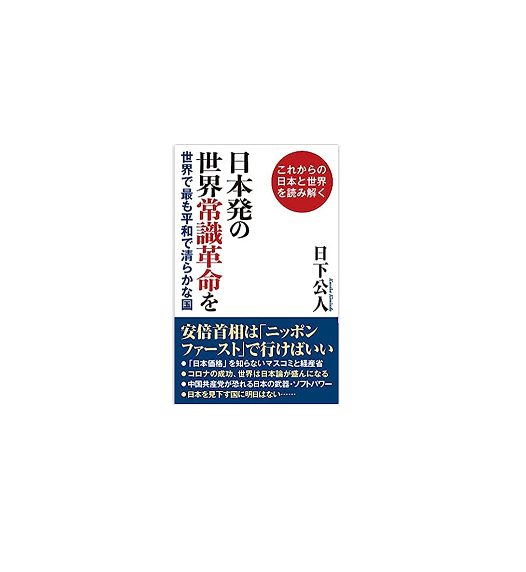
コメント